/magazine/6932.html
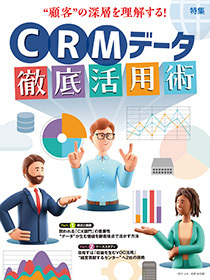
“顧客”の深層を理解する!
「CRMデータ」徹底活用術
Part.1 <現状と課題>
問われる「CX部門」の重要性
“データ”が生む価値を顧客接点で活かす方法
コールセンターに集積しているVOC、Eコマース含むWebサイト上の行動、営業店でのやり取りなど、データ活用が加速しつつある。コールセンターでも、応対履歴の確認にとどまらない、プロアクティブなサポートやアップ/クロスセル、離反防止に活かす取り組みが増えている。カギとなるのは、「データ統合・分析」の組織的・全社的な取り組みだ。データ活用の現在地と課題を検証する。
コールセンターをはじめ、顧客接点で得られるデータは「宝の山」──こう言われて久しい。しかし、この約20年間、必要性が提唱されてもなお、部門(組織)、チャネルごとに散在するデータが完全に統合されたケースは稀(まれ)だ。
コロナ禍を経て、消費活動がデジタルシフトするに伴い、ようやくその動きが加速している。
データ活用は、生産性向上や営業・販売力の強化、製品・サービスの機能改善、新たなCXの創出などさまざまな成果をもたらす。
CX向上を柱にデータ活用を進めるには、まずカスタマージャーニーを描き、商品検討から購入前相談、契約、商品の利用、アフターサポートなど、あらゆるタッチポイントのデータを網羅的に集約することが欠かせない。抽出したデータをカスタマージャーニーにマッピングすれば、具体的なペインポイントが把握できる(図1)。
本誌では、データ活用のボトルネックを解消するための、組織体制やソリューション活用、人材要件について、事例と専門家のアドバイスをもとに検証する。
図1 カスタマージャーニーのペインポイントを解消する
※画像をクリックして拡大できます
Part.2 <ケーススタディ>
目指すは「収益を生むVOC活用」
“経営貢献するセンター”へ2社の挑戦
コールセンターで日々集積される膨大なデータを収益向上に活かす。業種業態・センター規模を問わず、すべてのマネジメントが目指すべき挑戦だが、センター単独の取り組みでは不可能に近い。Part.2では、CRMデータをもとに経営貢献した事例として、老舗の大手保険会社である、あいおいニッセイ同和損害保険、成長著しいスタートアップであるfreeeの取り組みを検証する。
CASE STUDY 1:あいおいニッセイ同和損害保険
データ分析から「ターゲット」を特定
営業代理店の業務効率化を支援
あいおいニッセイ同和損害保険は自社内データの分析結果を、営業課支社・代理店の支援に活かしている。保有データの一元管理が必要と判断し、コンタクトセンター事業部内に「アナリティクスグループ」を設置した。
同グループの分析は、センターに集積されるコールログや対応履歴のほか、他部門で管理する情報も含まれる。分析手法は図2の通り。顧客の属性・特徴を把握したうえで、加入見込度の高い「人物像」を作成。得られたデータに基づき、満期を迎える契約者リストと照合し、加入見込度をランク付けしていく。
図2 分析手法を活用した営業スタイル
(あいおいニッセイ同和損害保険)
※画像をクリックして拡大できます
CASE STUDY 2:freee
SVが見やすい形にデータをビジュアル化
改善点を把握しエフォートレスを追求
クラウド会計ソフトウエア大手のfreeeは、顧客応対時に得られるVOCをはじめとしたデータの収集・分析に注力。分析結果を製品・サービス改善に活かすことで、“そもそもサポートを必要としない”エフォートレスなサービスの提供を目指している。
より高度な分析を実施するため、新たにBIツールを導入したほか、データ基盤構築チームを設立した。BIツールの運用画面は図3の通り。最新の顧客履歴をもとにしたグラフを社内で共有できるだけでなく、ハイライト表示やヒートマップなどの機能でビジュアル化されたグラフによって、迅速な状況把握が可能になり、仮説・検証へ至るフローが大幅に簡素化された。
図3 VOC分析に活用しているTableauの運用画面
※画像をクリックして拡大できます